旧法賃借権は買ってはいけない?その理由、知っていますか?
「安い物件を見つけたけど旧法賃借権って書いてある…」そんな方は要注意です。
思わぬトラブルや損につながる可能性もあるので、事前に知識を持つことが大切です。
 筆者
筆者この記事では「旧法賃借権買ってはいけない」と検索した人が、購入の判断基準をしっかり理解できます。
- 旧法賃借権の特徴や他の借地権との違い
- 購入前に知っておきたいデメリットや注意点
- 資産価値やローンの通りやすさなどの現実的な問題
- 買うべきかやめるべきかの判断ポイント


この記事を書いた調査隊長です。
論文・アンケート・実地調査をもとに「〜してはいけない」という噂の真偽を明らかにします。
この記事は消費者庁や国民生活センター・厚生労働省の発信情報を参考にし、コンテンツ制作ポリシーに則り作成しています。
旧法賃借権は買ってはいけない?注意点と判断基準
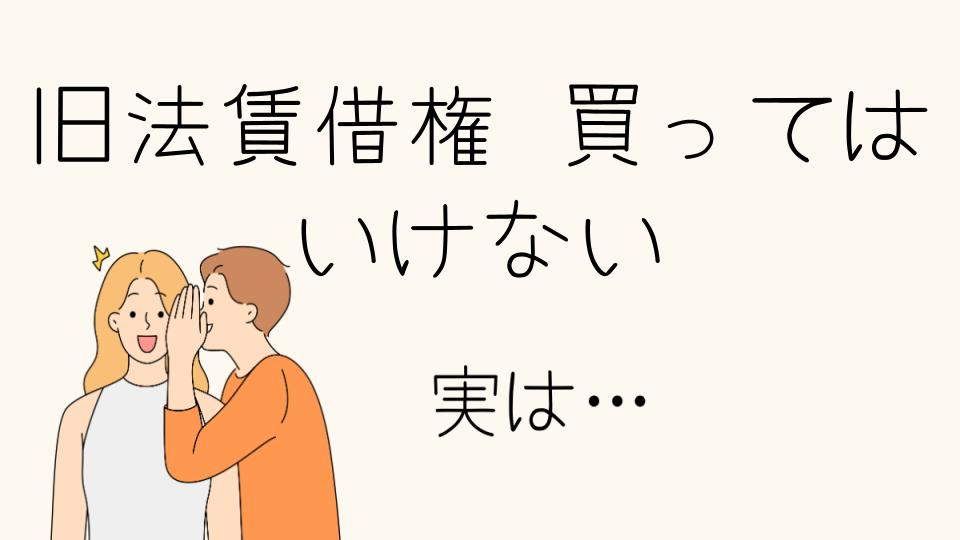
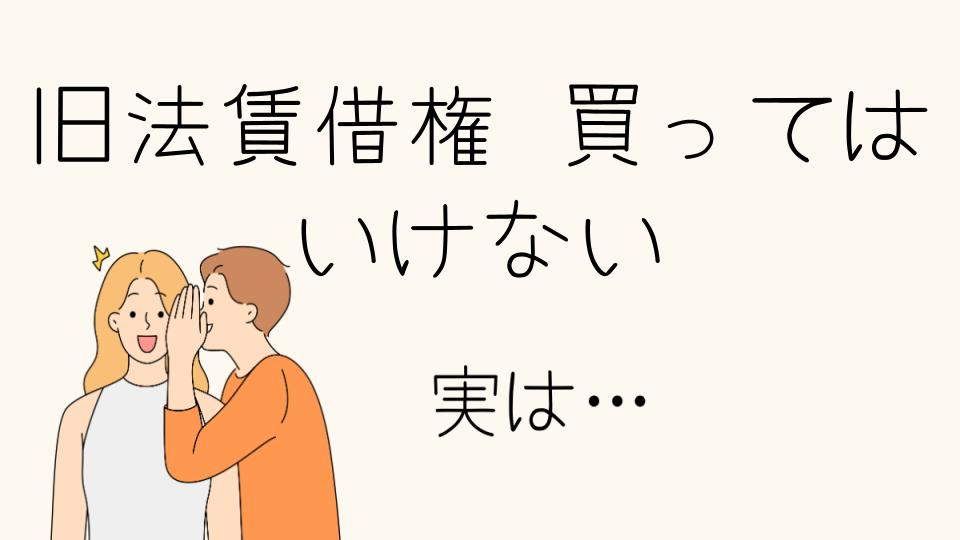
「旧法賃借権」は買ってはいけないとされる理由には、長期的なリスクがあるからです。この制度は、1992年より前に契約された土地の借り方に関するもの。住み続けられる安心感がある一方で、面倒なトラブルに発展することもあります。
たとえば、更新のたびに地主との交渉が必要だったり、建て替えにも許可が必要だったりと、自由がきかないのが現実です。買った後に「想像と違った」と後悔する人も少なくありません。
一方で、物件価格が安く手に入りやすいというメリットも存在します。固定資産税がかからないなど、コスト面では魅力があるのも事実です。
つまり、旧法賃借権の物件を買うかどうかはメリットとデメリットを冷静に見極めることが重要です。リスクをしっかり理解したうえで判断しましょう。
旧借地権の仕組みと特徴を知ろう
旧借地権とは、1921年にできた「旧借地法」に基づいて土地を借りる仕組みです。この法律は1992年に廃止されましたが、それ以前に結ばれた契約には今も適用されます。
この制度の最大の特徴は、借り手(借地人)の権利がとても強いことです。地主が「土地を返してほしい」と言っても、正当な理由がなければ断ることができるんです。
また、借り手は契約更新を何度でも行うことができ、半永久的に住み続けられるという大きなメリットがあります。これは家を持ちたい人にとっては安心材料になります。
しかし、良いことばかりではありません。たとえば土地を売りたいとき、地主の許可が必要だったり、高額な「承諾料」が発生することもあります。
さらに、銀行によっては旧借地権の物件では住宅ローンの審査が厳しくなるケースもあります。理由は、土地が借り物なので、資産価値が下がると見られるからです。
「地代」「更新料」「名義変更料」など、住んでからもお金がかかるのも特徴です。知らずに購入すると、思ったよりコストがかさむことも。
まとめると、旧借地権はルールを理解して使いこなせば有利ですが、初心者にはややハードルが高い制度かもしれません。



借地って、まるで“借りぐらしのアリエッティ”みたいに、人の土地で暮らす感覚にちょっと似てるんです。
旧借地権マンションで後悔する理由
旧借地権付きマンションで「後悔した」と感じる人の多くは、自由がきかないことに悩まされます。建て替えやリフォームをしたいと思っても、まずは地主の許可が必要です。
さらに、マンションを売却したくてもスムーズに進まないケースも。なぜなら、買い手が見つかりにくいから。旧借地権に詳しくないと、「なんか難しそう…」と敬遠されてしまうんです。
地代や更新料など、定期的に支払う費用が想定より多くて負担になることもあります。所有していてもずっとお金がかかることに不満を感じる人もいます。
住宅ローンもネックです。金融機関によっては、借地権付きの物件には融資をしない方針のところもあり、ローンが組めず断念することも。
また、契約書の内容が古く、現代の法律に対応していない場合もあります。そのせいでトラブルに発展することも少なくありません。
賃貸と違って、気に入らなくても簡単には引っ越せないのも大きなデメリット。「こんなはずじゃなかった…」と思っても、どうにもできない状況に陥ることも。
購入前に専門家にチェックしてもらうことがとても大切です。特に、契約内容や地主との関係性は事前にしっかり確認しましょう。



「安物買いの銭失い」にならないように、安さだけで飛びつかないのが賢い選択です。
借地権のトラブル事例から学ぶ教訓
借地権には、思わぬトラブルがつきものです。たとえば、借主が建て替えを希望した際に、地主から許可が下りず困ったという事例があります。
このようなトラブルは、契約内容をよく読まなかったことが原因です。特に古い契約書には、あいまいな表現が多く、解釈に差が出やすいんです。
別の事例では、地主と借主の間で地代の値上げを巡って裁判になったケースもあります。話し合いで解決できないと、関係が悪化してしまいます。
また、借主が第三者に借地権を譲ろうとしたとき、地主が「知らない人には貸したくない」と拒否。結果として売却ができなくなった人もいました。
このような問題を避けるためには、契約前に専門家に内容を確認してもらうことが大切です。弁護士や不動産のプロに相談しておくと安心です。
とはいえ、すべての借地が危険というわけではありません。誠実な地主さんとの関係性が築ければ、スムーズに話し合いが進むこともあります。
結局のところ、トラブルの多くは「知らなかった」「確認しなかった」ことから起こるので、下調べを怠らないことが何よりも大切です。



借地権は人間関係もセットで買うもの。契約書と同じくらい、相手を見ることも大事です。
地主に買ってもらう交渉の難しさ
借地権付きの物件を手放したいとき、「地主に買ってもらえたら楽」と思う方も多いです。でも、実はその交渉が一番難しいこともあるんです。
というのも、地主には買い取る義務がないから。相手の気持ち次第で、話が進まないこともあります。
また、地主の中には「将来、子どもに相続させたい」と考えている人も多く、手放す気がない場合もあります。こうなると交渉自体がスタートしません。
仮に話が進んでも、価格面で折り合いがつかないケースが多いです。借地権の価格はあいまいで、相場も地域によってバラバラです。
交渉を有利に進めるためには、査定書を用意したり、不動産会社に仲介してもらったりすることが有効です。
とはいえ、地主が感情的に拒否している場合、どんなに準備しても進展しないこともあります。冷静な対応が求められます。
成功するためには、相手の立場や考え方を理解する「気配り」がカギです。ただの値段交渉ではなく、信頼づくりがスタートラインです。



土地の交渉って、実は「心の交渉」でもあるんです。丁寧な言葉ひとつが、未来を変えるかも。
旧法賃借権のデメリットとは何か
旧法賃借権は、借主に有利すぎる制度とも言われます。そのせいで、地主との関係がギクシャクすることが多いんです。
たとえば、正当な理由がなければ契約を更新できてしまうため、地主が「土地を返して」と言っても断られることがあります。
そのため、地主が土地を有効活用できず、トラブルの原因になることもしばしば。関係が悪化すれば、日常生活にも影響します。
さらに、建て替えや売却のたびに地主の「承諾料」が必要なことも。これが高額になり、出費に悩まされる方も多いです。
また、住宅ローンが通りにくいという問題もあります。金融機関によっては、担保価値が低いと判断されてしまうんです。
契約書の内容が昔のままで、現在の法律と合わないこともあります。そのせいで解釈の違いからもめることもあるんです。
もちろん、物件価格が安かったり、固定資産税がかからなかったりと、良い面もありますが、デメリットの大きさを軽視するのは危険です。



いい条件に見えるほど、ウラに注意点があることも。安い=お得ではないって覚えておいてくださいね。
旧法賃借権は買ってはいけないのか?冷静に見極めるポイント
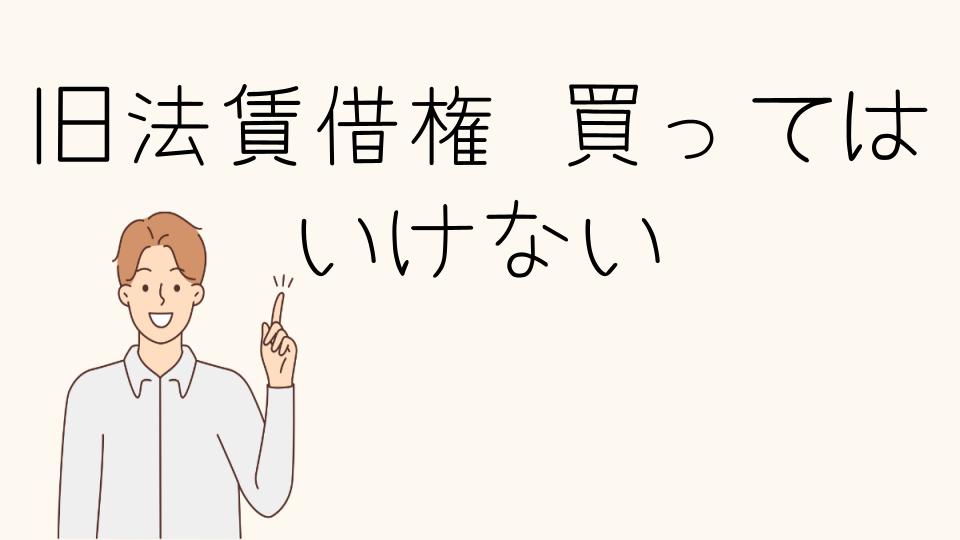
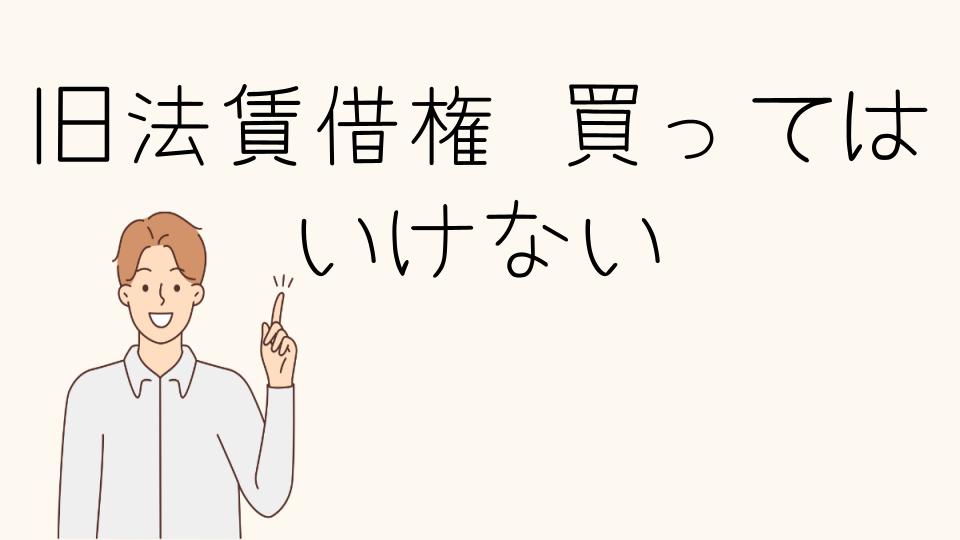
「旧法賃借権=買ってはいけない」とは一概に言えません。条件次第では、良い選択になることもあります。
旧法賃借権は借り手にとって有利な契約です。契約を更新し続ければ、長く住み続けることができます。
ただし、地主の許可が必要な場面が多く、自由にリフォームや売却ができない点には注意が必要です。
購入を検討するなら、「費用対効果」と「自分のライフプラン」に合うかどうかを冷静に判断しましょう。
旧借地権マンションの資産価値を検証
旧借地権付きマンションは、土地の所有権がない分、価格が安く設定されています。最初の出費は抑えられます。
しかし土地の資産価値が含まれていないため、売るときには高値がつきにくいという現実があります。
また、マンションの築年数が古いことも多く、修繕積立金や管理費が高くなる傾向にあります。
金融機関からの住宅ローン審査も厳しくなることがあり、現金購入を求められるケースもあります。
一方で、都心や駅近など、立地の良い物件が多いのは魅力です。立地を重視するなら選択肢のひとつになります。
ただし、建物の老朽化や土地返還時のトラブルも起こりやすいため、長期的な視点で判断が必要です。
総合的に見ると「安く買えて便利に暮らせる」が魅力ですが、「資産価値は限定的」と考えておきましょう。



目先の安さに飛びつくより、将来の売却や資産としての価値まで見て判断するのがコツです。
定期借地権との違いで損しないために
旧法賃借権と定期借地権の違いを知ることは、とても大切です。混同すると大きな損をする可能性があります。
旧法賃借権は借主にとって有利で、契約を更新し続けられる可能性が高いという特徴があります。
一方で、定期借地権は更新ができず、契約が終わったら必ず土地を返す必要があります。
つまり、定期借地権の物件は「住み続けられる期間」が決まっているので、終の住まいには向いていません。
また、定期借地権付きマンションでは、建物の解体費用を積み立てておく必要があるなど、別の負担も発生します。
とはいえ、定期借地権のほうが地主とのトラブルが少なく、将来計画が立てやすいというメリットもあります。
旧法と定期、どちらが良いかは、自分の目的やライフプランによって大きく変わってきます。



「どちらが正解」ではなく、「どちらが自分に合うか」で選ぶのが不動産選びの第一歩です♪
借地権付き住宅の住宅ローンの難しさ
借地権付き住宅を購入する際、一番のハードルになるのが住宅ローンの審査です。
土地を所有していないため、銀行が担保として評価しにくく、融資を断られることもあります。
とくに旧借地権など、法的に複雑な契約が絡むと、金融機関は慎重になりがちです。
融資が可能でも、通常よりも金利が高くなったり、融資額が減ることがあります。
一方で、一部の銀行では借地権専用のローン商品を用意している場合もあります。
そのため、事前に金融機関へ相談し、どのくらい借りられるかを把握しておくことが大切です。
物件選びと同時に、ローンの可否も確認しながら進めるのが賢い方法です。



「土地がない=ローン不可」ではないですが、通すには戦略が必要です♪
旧借地権にある隠れたメリットとは
旧借地権はデメリットばかりと言われがちですが、実は隠れたメリットもあるんです。
一番の魅力は、土地代が不要なため、購入時の費用を大きく抑えられることです。
固定資産税や都市計画税も地主が払うため、住んでいる間のコストも意外と低めです。
また、都心や駅近など、好立地な物件に安く住めるケースが多いのもメリットです。
さらに、借り手の権利が強く、長く住み続けられる可能性が高い点も安心材料になります。
ただし、地主の許可が必要な場面があるため、自由に使いたい人には向かないかもしれません。
自分にとって「コスパ重視」か「自由重視」かを考えることで、旧借地権の価値が見えてきます。



人によっては“賢く住める裏ワザ物件”になることもあるんですよ!
借地権物件の賢い選び方と対策
借地権付きの物件を選ぶなら、まずは「どの種類の借地権なのか」を確認しましょう。
旧法か新法か、定期借地権かで、住める期間や更新の可否が大きく変わります。
次に、残りの契約期間がどれくらいあるかもチェックしましょう。短すぎると再契約が必要になります。
また、建て替えや増改築に地主の承諾が必要かどうかも重要なポイントです。
契約内容が不明確な場合は、専門家に相談するのが安心。契約書のチェックも忘れずに。
購入後にトラブルを避けるためには、費用の内訳や将来の更新条件を明確にしておきましょう。
情報をしっかり集めて比較することが、失敗しない物件選びの第一歩です。



「安い」だけで決めるのは危険!借地権こそ慎重な目利きが必要です。
まとめ|【後悔】旧法賃借権は買ってはいけない?損しない見極め方を徹底解説
最後にこの記事のポイントをまとめてご紹介します。
- 旧法賃借権は権利が強く更新も可能な一方で流動性が低い
- 住宅ローンが組みにくく購入資金に制限が出る可能性がある
- 地代や承諾料などの支払いが長期的に重荷になるケースもある
- 建て替えや売却には地主の許可が必要で自由度が低い
- 旧借地権付きマンションは資産価値が下がりやすい傾向にある
- 契約内容が不明確だとトラブルのもとになりやすい
- 地主との交渉や名義変更がスムーズに進まないことがある
- 一方で土地代が不要で初期費用が安く済むという利点もある
- 借地権の種類や残存期間を正確に把握することが重要
- 安さに惑わされず総費用や将来のリスクを冷静に判断すべき
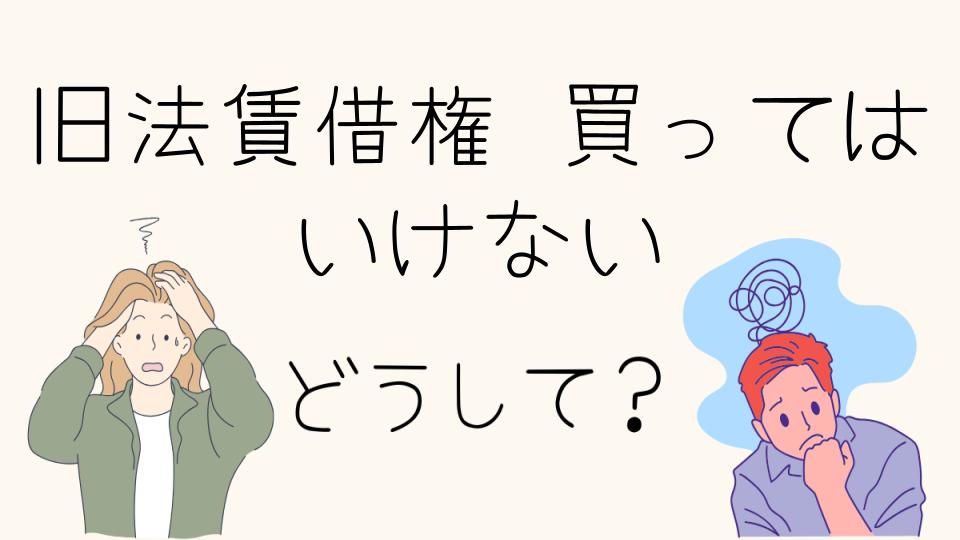
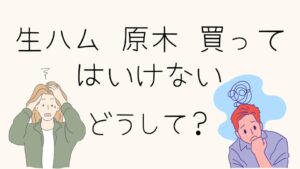
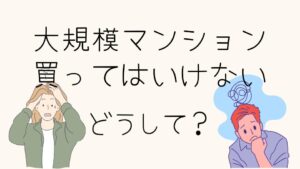
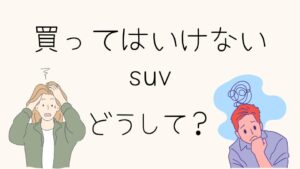
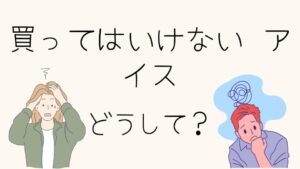
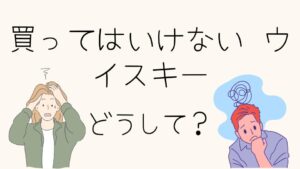
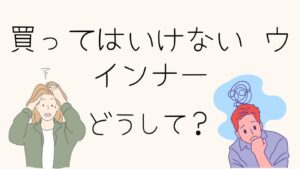
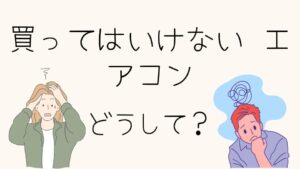
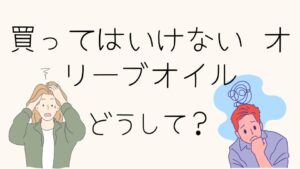
コメント