「ハムスター 買ってはいけない」と検索する前に知っておきたいことがあります。
ハムスターは手軽に飼えると思われがちですが、実は注意点もたくさんあります。
性格や生活スタイルによっては、後悔することもあるんです。
 筆者
筆者この記事では、ハムスターを買ってはいけない理由と、飼う前に知っておくべきポイントを分かりやすく紹介します。
- ハムスターが向いていない人や家庭の特徴
- 飼って後悔する理由とその対策
- 騒音・費用・寿命に関する注意点
- 飼育環境の整え方と虫の発生リスク


この記事を書いた調査隊長です。
論文・アンケート・実地調査をもとに「〜してはいけない」という噂の真偽を明らかにします。
この記事は消費者庁や国民生活センター・厚生労働省の発信情報を参考にし、コンテンツ制作ポリシーに則り作成しています。
ハムスターを買ってはいけない理由とその背景


ハムスターは小さくて可愛いペットとして人気がありますが、誰にでも飼えるわけではありません。飼い始めてから「思っていたのと違う…」と感じる人も少なくありません。
実は、ハムスターには夜行性・繊細・短命といった特徴があります。このため、生活リズムが合わなかったり、期待していたほど触れ合えなかったりすることも。
さらに、ケージの掃除や温度管理といったお世話も必要です。可愛いだけで飼ってしまうと、日々の世話が負担に感じてしまうことがあります。
もちろん、ちゃんと理解して準備すれば素敵なパートナーにもなれます。ただし、飼う前にはしっかりと現実を知っておくことが大切です。
ハムスター飼わなきゃよかったと感じる瞬間
「癒されたいから」と思って飼い始めても、すぐに理想と現実のギャップを感じることがあります。ハムスターは犬や猫のように懐くわけではありません。
昼間はほとんど寝ていて、夜中に活発になります。そのため「遊べる時間が少ない」と感じる人もいます。特に夜に音が気になる方にはつらいかも。
また、思っていたよりもケージの掃除が大変と感じる人も多いです。特に夏場はにおいや湿気が気になり、頻繁な清掃が必要になります。
さらに、2〜3年という短い寿命もネック。情が湧いた頃にお別れが来ることを考えると、ペット初心者にはつらい経験になることもあります。
子どもがいる家庭では、別れをきっかけにペットロスになるケースも少なくありません。事前に「いつかお別れがある」という心構えも大切です。
また、複数飼いをして思わぬ繁殖トラブルになることもあります。オスメスの区別が難しいので、飼う時はよく確認しましょう。
もちろん全てがマイナスではなく、静かに見守るのが好きな人にはピッタリな存在です。性格や生活スタイルによって合う合わないが大きいですね。



「可愛い=飼いやすい」ではありません。自分の生活とマッチするかどうか、じっくり考えることが大切です。
ハムスターが溶けるのはなぜ?暑さ対策の重要性
暑くなってくると、ハムスターが体をペタッと伸ばして寝ている姿を見ることがあります。これは一見かわいく見えますが、実は暑さに耐えているサインなんです。
ハムスターは体温調節が苦手な動物です。汗をかかないため、体の熱をうまく逃がすことができません。そのため、室温が高くなるとすぐに体調を崩してしまいます。
「溶けるように見える寝方」は、体を冷やそうとする行動のひとつ。暑さが限界に近づくと、熱中症になることもあります。
ハムスターが熱中症になると、ぐったりしたり、呼吸が荒くなったりします。こうなった時はすぐに温度を下げるなどの応急処置が必要です。
そのためには、エアコンや保冷グッズでの温度管理がとても重要です。冷却プレートや保冷剤を使うと、体を冷やすスペースを作ってあげられます。
ただし、保冷剤は直接触れると危険なので、タオルで包んだり、ケージの外に置いたりしましょう。冷やしすぎも禁物なので、程よい温度が大切です。
夏場は室内の温度が30度を超えることもあるため、できれば常にエアコンをつけておくのが理想です。少しの電気代で命が守れるなら、安いものですよね。



「溶けてる=可愛い」は要注意。ハムスターにとっては命の危機かも。夏場は“涼しい巣作り”を意識して!
ハムスター買ってはいけない人の特徴
ハムスターを飼う前に、自分の性格やライフスタイルを見直してみましょう。全ての人に向いているペットではありません。
例えば、こまめなお世話が苦手な人には不向きです。エサやりや掃除など、毎日のケアが必要だからです。
夜しっかり眠りたい人にも向いていません。ハムスターは夜行性で、ケージの中でカラカラと音を立てて動き回ります。
「たくさんスキンシップしたい」と思っている人も要注意。ハムスターは基本的に触られるのが苦手な動物です。
旅行が多かったり、不在がちな人も避けたほうが無難。急に世話を頼める人がいないと、体調を崩す原因になります。
また、経済的に余裕がない場合も慎重に。医療費や冷暖房代など、意外と出費がかさむことがあります。
大切なのは「可愛いから飼いたい」ではなく、「最後まで責任を持てるかどうか」という視点です。



子どものお世話と同じで、覚悟がないと長続きしません。お迎え前に、自分に問いかけてみてくださいね。
ハムスター飼わない方がいい家庭環境とは
ハムスターを迎える前に、住環境も大切なチェックポイントです。飼育に適さない家庭もあることを知っておきましょう。
まず、ペット不可の賃貸物件に住んでいる場合は要注意。ハムスターもペットに含まれることが多く、規約違反になる恐れがあります。
小さなお子さんがいる家庭では、思わぬ事故が起きることも。強く触ってしまったり、驚かせたりすると、ケガやストレスの原因になります。
家の中に猫や犬などの他の動物がいると、ハムスターにとっては強いストレスになることがあります。場合によっては命の危険も。
通気性が悪かったり、温度管理が難しい部屋にケージを置くのも避けたいところです。特に夏や冬は命に関わります。
日中家に誰もいない時間が長く、温度チェックや水の補充ができない場合も、飼育は難しいかもしれません。
さらに、家族の中に動物アレルギーがある場合は慎重に検討を。毛や床材がアレルゲンになることがあります。



静かな環境・安定した温度・安全な場所。この3つがそろってこそ、ハムスターにとって快適な住まいになります。
ハムスターを飼うとゴキブリが出るって本当?
「ハムスターを飼うとゴキブリが出る」なんて話、気になりますよね。実は、飼育環境によっては本当のこともあるんです。
ハムスターのケージには、エサや床材がたくさんあります。これらが放置されたり湿ったりすると、ゴキブリの格好の住処になります。
特に野菜などの生ものを入れっぱなしにすると、腐ってゴキブリを呼び寄せてしまう可能性があります。
でも安心してください。きちんと掃除をすれば、ゴキブリの心配はぐんと減ります。大事なのは「清潔な飼育環境」です。
週1回の大掃除に加えて、食べ残しのチェックや水漏れの防止を心がけましょう。重曹や自然な虫よけも効果的です。
「それでも出てきてしまった…」という時は、ペットに安全な虫除けグッズを選ぶことが重要です。市販の強い薬剤は避けましょう。
つまり、ハムスターそのものがゴキブリを呼ぶわけではなく、管理が甘いと招いてしまうということ。飼い主の心がけがすべてです。



虫嫌いさんはちょっとドキッとしちゃいますよね。でも大丈夫。こまめな掃除こそ、ハムスターにも自分にも安心の近道です!
ハムスター買ってはいけないケースと対策
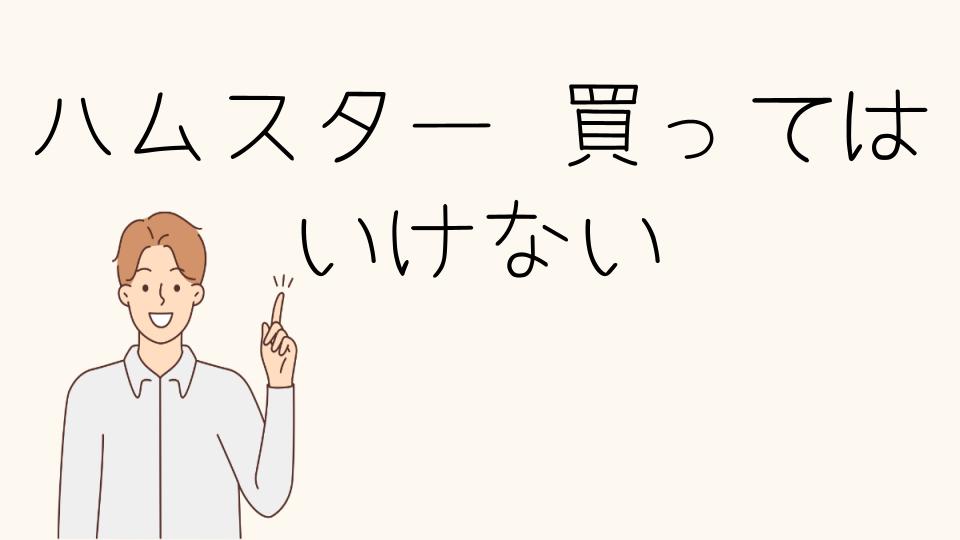
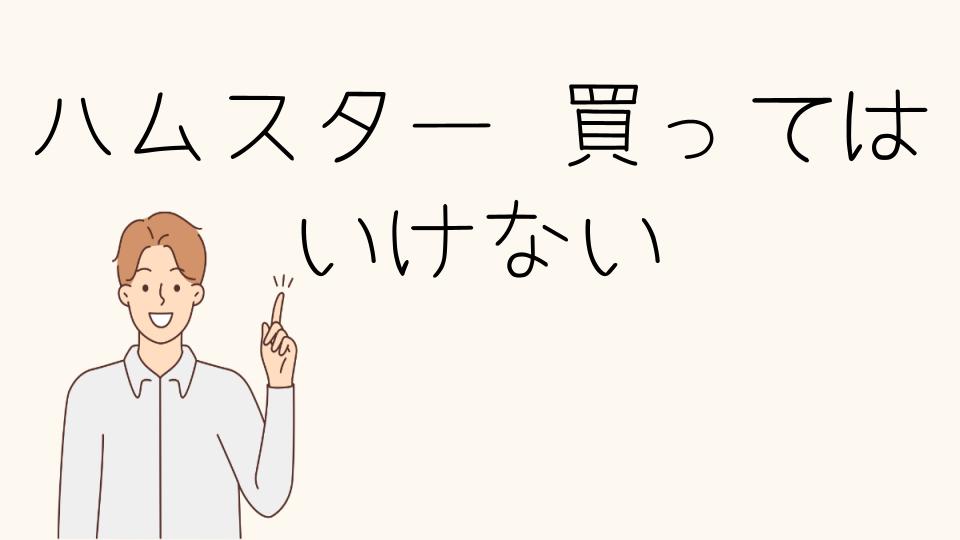
ハムスターは手軽に飼えるイメージがありますが、実際は「買わない方がいいケース」も存在します。事前に確認しておくことが大切です。
たとえば、「忙しくて世話ができない」「環境が整っていない」「知識が足りない」などがよくあるパターンです。
ただし、これらは全て事前の準備や心構えで乗り越えられることでもあります。知識をつければ、問題を回避できます。
「買って後悔した」とならないためには、ハムスターに合った環境と自分に合った飼い方を見つけることが重要です。
ハムスター買ってはいけないおもちゃの例
ハムスター用のおもちゃはたくさんありますが、中には買ってはいけない危険なものも存在します。
一番多いのは、金網タイプの回し車です。足が隙間に挟まってしまい、ケガや骨折につながることがあります。
また、2階建ての高い遊具も要注意です。ハムスターは高い場所が苦手で、落ちてしまうと大けがの原因になります。
トンネル系のおもちゃも、小さすぎたり長すぎるものは、中で詰まったり温度がこもったりして危険です。
カラフルな塗装がされたおもちゃにも気をつけましょう。口に入れてしまうと、塗料が体に悪影響を与えることも。
安全なおもちゃを選ぶには、「足がはさまらない」「落ちにくい」「通気性がある」などがポイントになります。
プラスチック製で丸い形の回し車や、低めのかじり木おもちゃなどが安全でおすすめです。



見た目の可愛さより「安全第一」で選びましょう。おもちゃでケガしてしまったら、本末転倒です。
ハムスターどこで買うかで差が出る理由
ハムスターはペットショップやブリーダー、里親募集など、購入場所によって健康や性格に違いが出ることがあります。
ペットショップは手軽に購入できますが、衛生面や育てられた環境にばらつきがあるため、注意が必要です。
良いお店では、清潔なケージ管理や体調管理をきちんとしており、スタッフも知識豊富です。
一方、値段が安いだけの店舗だと、病気を持っていたり、ストレスの多い環境で育っている場合もあります。
ブリーダーから購入する場合は、個体の性格や親の健康状態も教えてもらえることが多く、安心感があります。
里親募集も選択肢のひとつです。ただし、過去の飼育環境が分かりづらいので、初心者には難易度が高いことも。
どの方法を選んでも、信頼できる相手から買うことが大切。実際に話を聞いたり、ケージの様子を見たりしましょう。



「どこで買うか」は、ハムスターの一生を左右する選択。信頼できる人から迎えると、安心感が違いますよ♪
ハムスターの寿命が短くて後悔する人も
ハムスターの平均寿命は2〜3年ほどとかなり短めです。見た目の可愛さから軽い気持ちで飼う人もいますが、お別れが意外と早くやってきます。
特に初めてペットを飼う人や子どもにとっては、命の終わりを受け入れるのが難しいこともあります。
「もっと一緒にいたかった」「慣れてきた頃にお別れが来た」と感じて後悔するケースも少なくありません。
一方で、短い寿命だからこそ毎日を大切に過ごせるという声もあります。限られた時間が絆を深めてくれるのも事実です。
大事なのは、飼う前にこの事実を知っておくこと。短命だからこそ覚悟と優しさが必要です。
どうしても長く一緒にいたいと思うなら、別の種類のペットを検討するという選択もあります。
どんな命にも終わりがあることを、きちんと受け止められるかどうかが飼い主としての覚悟になります。



ハムスターの命は「季節が2〜3回変わるくらい」。短いけど、そのぶん濃い時間が過ごせますよ。
静かな夜を過ごしたい人に向かない理由
ハムスターは夜行性の動物。つまり、人が寝る時間に活動し始めるという特徴があります。
暗くなると元気になり、回し車を回したり、カサカサとケージ内を走り回る音が聞こえます。
この音は意外と響くので、寝室にケージを置くと「音がうるさくて眠れない」という人も少なくありません。
とくに静かな環境でしか眠れないタイプの人には、かなりストレスになることがあります。
もちろん、静音タイプの回し車や防音グッズを使うことで音を軽減する方法もあります。
別の部屋にケージを置くことで解決できるケースも多いです。住まいの間取りによって対応は可能です。
ただ、「夜は完全な静寂がないと寝られない」という人には、ハムスターとの生活は合わないかもしれません。



「小さな音でも眠れない人」は要注意!夜の活動がハムスターにとっての“本番”なんです。
飼育費用が意外とかかるって知ってた?
ハムスターは体が小さいからといって、飼育費用が安いとは限りません。毎月コツコツ出費が続きます。
エサ代は月に1,000円ほどですが、床材やトイレ砂の交換も必要なので、合計で2,000〜3,000円程度かかることが多いです。
さらに、夏や冬にはエアコンを常時つける必要があり、電気代がアップすることもあります。
病気になれば、診察代や薬代がかかります。小さな体ですが、医療費は意外と高めで、1回5,000円以上かかることも。
初期費用としても、ケージ・回し車・餌入れ・給水器などで1万円近くかかることも珍しくありません。
「1000円で買えるなら、安く済むだろう」と思いがちですが、実際には飼い始めてからの方がお金がかかります。
「小さな命にも大きな責任と費用が必要」という意識が大切です。費用面でも事前の確認は必須ですね。



「安く済むと思ってた…」と後悔する前に、毎月かかるお金をしっかりイメージしておくことが大切です♪
まとめ|【後悔】ハムスターは買ってはいけない理由10選と対策
最後にこの記事のポイントをまとめてご紹介します。
- ハムスターは夜行性で騒音が睡眠を妨げることがある
- 寿命が短く、情が湧いた頃にお別れが来る
- 飼い主の生活スタイルに合わないと後悔しやすい
- 意外と飼育費用がかかり、医療費も高めになる
- お世話が毎日必要で、忙しい人には向いていない
- 掃除を怠るとゴキブリなどの害虫が発生するリスクがある
- 高所や金網など危険なおもちゃを使うとケガの原因になる
- どこで購入するかによって健康状態や性格に差が出る
- ペット不可の物件や音が多い家庭には不向き
- 小さな子どもや動物アレルギーのある家庭は注意が必要
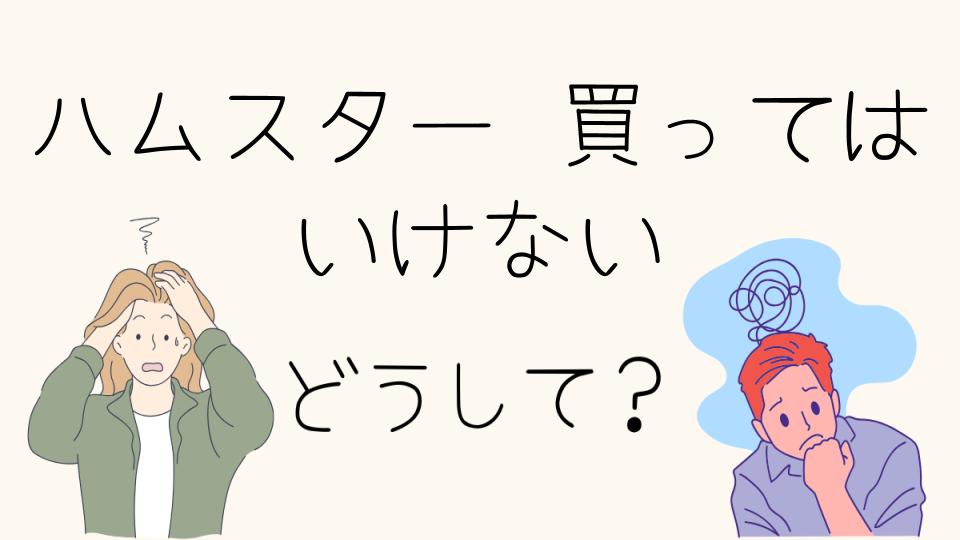
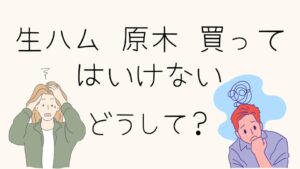
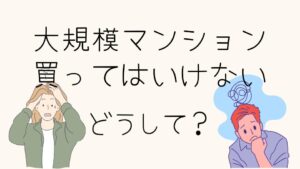
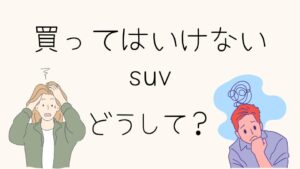
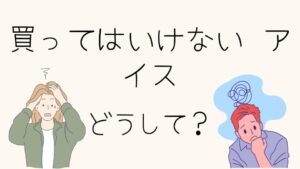
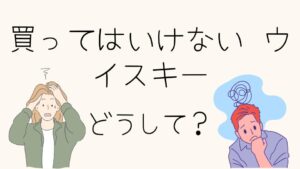
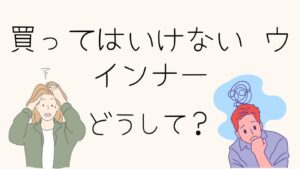
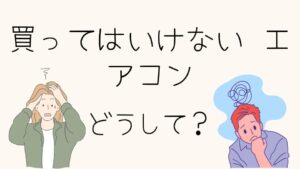
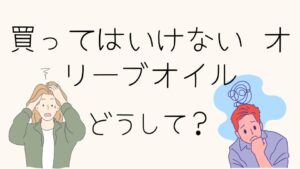
コメント