エアコン買ってはいけないサイズ、選び方を間違うと損します!
「とりあえず畳数どおりでいいかな?」と思っていませんか?
実は、それだけで選ぶと電気代がムダに高くなることもあるんです。
 筆者
筆者この記事では、エアコン買ってはいけないサイズの落とし穴と適正な選び方がわかります。
エアコンを買ってはいけない時期については下の記事をチェック!
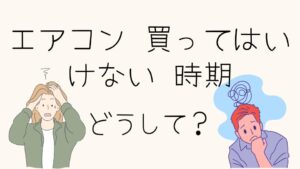
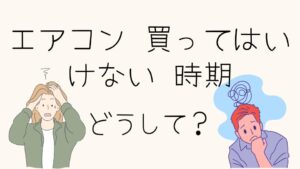
- エアコンを畳数だけで選ぶ危険性
- マンションと戸建てでサイズ選びが違う理由
- 適正サイズが電気代にどう影響するか
- 避けるべき購入タイミングとその理由


この記事を書いた調査隊長です。
論文・アンケート・実地調査をもとに「〜してはいけない」という噂の真偽を明らかにします。
この記事は消費者庁や国民生活センター・厚生労働省の発信情報を参考にし、コンテンツ制作ポリシーに則り作成しています。
エアコン買ってはいけないサイズの落とし穴
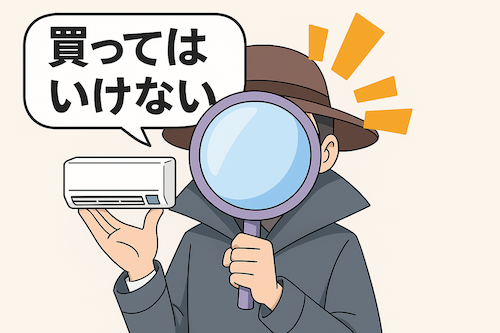
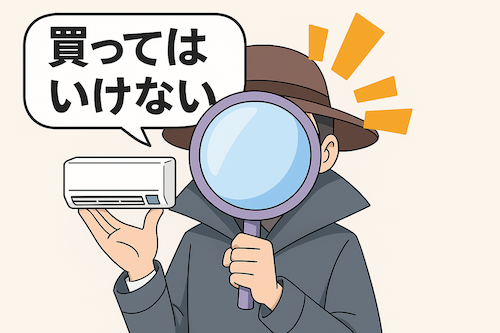
「エアコンのサイズなんて、部屋の畳数で選べばいいでしょ?」と思っていませんか?実はその考え、ちょっと危険かもしれません。
なぜなら、エアコンの畳数表示は「昔の家」を基準に作られていることが多く、現在の高気密・高断熱の家とは相性がよくない場合があるからです。
そのため、畳数表示だけで選ぶと「効きすぎる」または「効かない」など、使いづらさを感じるケースが増えています。
今回は、エアコンのサイズ選びで陥りやすいミスや、避けたいパターンについて詳しく解説します。
エアコン20畳に14畳用は本当にNG?
結論から言うと、家の性能によっては20畳の部屋に14畳用のエアコンでも問題ないケースがあります。
最近の家は、断熱性・気密性がとても高くなっています。そのため、熱が外に逃げにくく、少ない出力でも室温を保てることが多いです。
特に「せやま基準」など、しっかりとした住宅性能をクリアしている家では、小さめのエアコンでも十分に部屋全体が快適になります。
ただし、間取りや日当たり、部屋の形状などによっては、出力不足になる可能性もあるので注意が必要です。
また、冷房は意外と小さいエアコンでも対応できるのですが、暖房はパワーが必要になることが多いです。冬場の快適さも考慮するべきですね。
14畳用で20畳をまかなう場合は、運転時間が長くなる傾向があります。そのため、結果的に電気代が高くなることも考えられます。
「一応動くけど、なんかイマイチ…」という状態にならないためにも、家の性能と実際の使用状況をよく見極めることが大切です。



性能の高い家なら小さめでもOK。でも冬の暖房は余裕を持たせるのが安心です!
エアコン畳数が合ってないとどうなる?
エアコンのサイズが部屋の広さに合っていないと、「効きが悪い」「すぐ止まる」「電気代が高い」などのトラブルが起こりやすくなります。
例えば、部屋より小さいサイズのエアコンを使うと、なかなか設定温度に届かず、フル稼働が続きます。その結果、無駄な電力を消費しやすくなります。
逆に大きすぎるエアコンは、すぐに設定温度に達してしまうため、こまめなオンオフを繰り返すことに。これもまた電気代が高くなる原因になります。
また、適正サイズでないと温度ムラが発生しやすく、「部屋の隅が冷えない」「ベッド周りだけ暑い」など、快適性が損なわれます。
温度調整がうまくいかないと、体調を崩す原因にもなります。特に子どもや高齢者がいる家庭では要注意です。
湿度管理にも影響があります。パワー不足だと除湿が足りずジメジメしがちになり、逆にオーバースペックだと乾燥しやすくなります。
快適さだけでなく、健康面やコスト面にも影響が出るため、畳数だけを鵜呑みにせず、家の条件に合ったサイズ選びがとても大切です。



大は小を兼ねないのがエアコン。ちょうどいいが一番です♪
マンションの畳数表示に要注意
マンションに住んでいる方がエアコンを選ぶとき、畳数表示をそのまま信じるのはちょっと危険です。
というのも、畳数表示は「木造住宅」と「鉄筋コンクリート造」で分かれているのをご存じでしょうか?
マンションは多くが鉄筋コンクリート造なので、木造に比べて断熱性や気密性が高く、冷暖房効率が良いといわれています。
そのため、6畳用と表示されていても、実際には8畳程度までカバーできる場合もあるのです。
ただし、角部屋や最上階、窓が大きいお部屋などは熱が逃げやすくなるので注意が必要です。
「同じ畳数でも環境によって効きが変わる」ということを意識して、購入前に設計士や販売員に相談するのも安心です。
畳数表示はあくまで目安。マンション特有の条件も踏まえて選ぶようにしましょう。



マンションは構造がしっかりしているから、小さめエアコンでも意外とイケちゃうかも♪
エアコン適正サイズの計算方法とは
エアコンのサイズ選びに迷ったときは、「計算」することで目安がはっきりします。
まず基本となるのが、部屋の広さ(畳数)です。これに、部屋の断熱性や方角などを加味します。
例えば、南向きで日当たりの良い部屋は、夏に熱がこもりやすいので冷房が効きづらくなります。
また、断熱がしっかりしている家なら、少ない出力でも快適に保てるため、ワンサイズ下でも対応できる可能性があります。
簡単に計算したい方には、「エアコン容量早見表」などのツールを使うと便利です。
さらに正確に知りたいなら、UA値(断熱)とC値(気密)を使った計算もありますが、これはプロの手を借りた方が安心かもしれません。
自分で計算するのが不安なときは、工務店や販売スタッフに「我が家に合うサイズ」を相談しましょう。



ざっくりの目安なら早見表、しっかり考えるならプロに相談!状況に合わせて使い分けてね♪
6畳用エアコンは何畳まで対応できる?
「6畳用エアコンって本当に6畳しか無理?」と思ったこと、ありませんか?実は条件次第で20〜30畳まで対応できる場合もあるんです。
というのも、エアコンの畳数表示は古い住宅基準で作られていて、現代の高性能住宅には当てはまらないことが多いんです。
特に「せやま基準」などをクリアしている家では、6畳用エアコンで30畳近くカバーできたという実例もあります。
それでも、誰の家でもそうなるわけではありません。例えば築年数が古い、断熱が不十分、窓が多いなどの場合は効きにくくなります。
また、夏と冬で対応力も変わります。冬の暖房はパワーが必要なので、注意が必要です。
過信しすぎると「効かない」「寒い」「電気代がかさむ」といったトラブルにもつながりかねません。
使える広さの目安は「家の性能+部屋の条件」で変わるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。



6畳用=6畳とは限らないけど、過信は禁物。住まいの性能を見極める目が大事です♪
エアコン買ってはいけないサイズの選び方
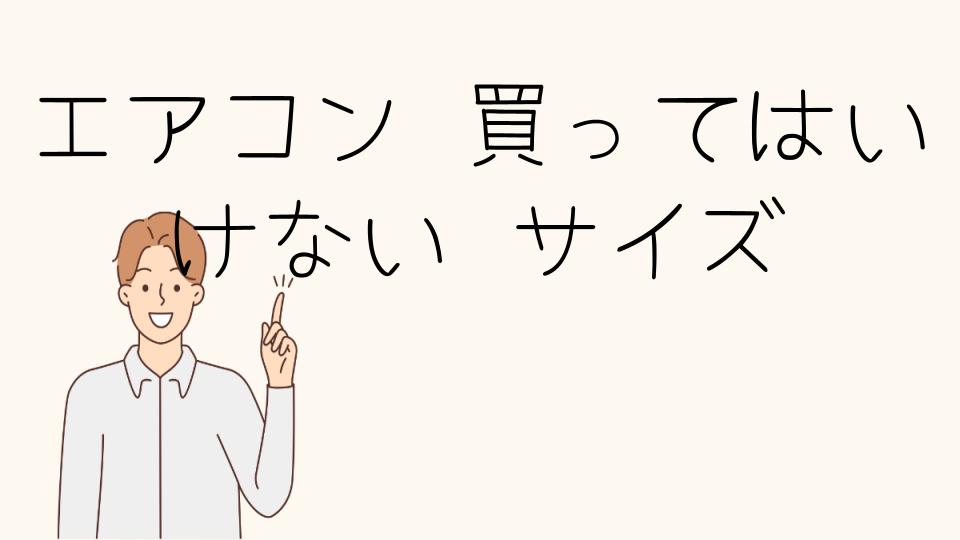
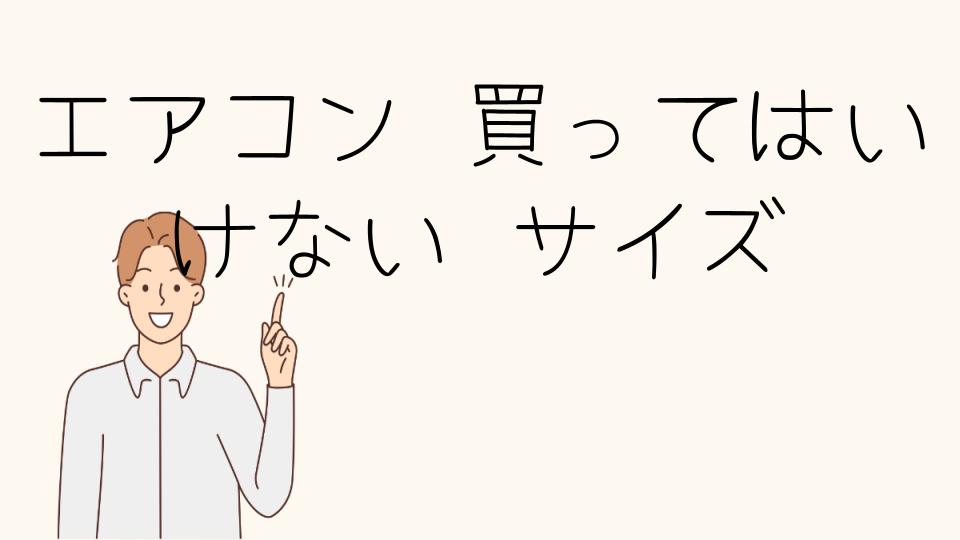
エアコンのサイズ選びで失敗しないためには、畳数だけを基準にしないことが大切です。
畳数表示はあくまで目安であり、部屋の構造や家の性能によって必要な出力は大きく変わります。
特に断熱性や気密性が高い家では、小さめサイズでも効きやすい傾向があります。
逆に、古い家や窓が多い部屋では、スペック通りでも効きが悪くなることもあります。
エアコンは「暮らし方」と「住まいの環境」に合わせて選ぶことが正解です。
エアコン大きめを買うのは正解?
「迷ったら大きめを買っておけば安心」と思っている方は多いかもしれません。
たしかに、出力が足りないよりは多少オーバースペックの方が安心感はあります。
ただし、大きすぎるエアコンにはデメリットもあります。温度調整がうまくできず、電気代が高くなることもあるのです。
とくに冷房時は部屋がすぐに冷えすぎてしまい、身体に負担がかかることも。
また、湿度調整がうまくできず、ジメジメ感が残る場合もあります。
エアコンが頻繁にオン・オフを繰り返す「短時間運転」になると、機械への負担も増えやすいです。
結論としては、「迷ったら大きめ」ではなく、「迷ったらプロに相談」がおすすめです。



大は小を兼ねる…とは限らないのがエアコン選び。むしろ“ちょうどいい”が一番コスパ良いですよ♪
エアコン買ってはいけないメーカーの特徴
どのメーカーのエアコンを選ぶかも大切ですが、避けたいのは「サポートが弱いメーカー」です。
エアコンは取り付け後の故障や不具合もあるため、サポート体制がしっかりしていないと後悔につながります。
また、聞いたことのない格安メーカーは初期コストは安くても、耐久性に不安が残ることもあります。
省エネ性能や静音性など、基本的な機能が劣っていることもあるため、安さだけで決めないようにしましょう。
さらに、部品供給が少ないと修理ができず、本体ごと交換になることもあります。
評価が不安定なメーカーや、口コミで「すぐ壊れた」という声が多い場合は慎重に判断するべきです。
価格・サポート・性能のバランスが取れているかを確認するのが、良いメーカー選びのコツです。



安かろう悪かろうにならないためにも、メーカー選びはレビューとサポート体制を要チェックです!
畳数だけでエアコンを選ぶ危険性
エアコンを選ぶとき、多くの人が「6畳用」「14畳用」などの表示を参考にします。
でも実は、この畳数表示はあくまで目安。実際の部屋の条件によって必要な性能は変わるんです。
たとえば、窓が大きくて日差しが強い部屋や、天井が高い部屋は冷暖房効率が下がります。
同じ6畳でも、建物の構造や断熱性、日当たりなどで必要な出力は全く異なります。
畳数通りに選んでも、エアコンの効きが悪いと感じるのはこうした理由からです。
結果的に「効かないから」と設定温度を下げて、電気代が余計にかかってしまうことも。
畳数+家の性能をセットで考えるのが、本当に満足できる選び方です。



「6畳=6畳の部屋にぴったり」ではないんです!冷暖房は“家の個性”もちゃんと見てあげましょう♪
エアコン買ってはいけない時期とは?
エアコンの価格は1年中同じではありません。「買ってはいけない時期」が確かに存在します。
たとえば、暑さが本格化する6〜7月や、寒くなる12月はエアコンの需要が急増します。
この時期は需要が高いため、セールも少なく、価格が高騰しやすい傾向にあります。
また、購入しても取り付け工事が混み合っていて、設置まで数週間待たされることも。
逆に、買い時と言われるのは8〜9月や2〜3月など、需要が落ち着いた季節です。
この時期は型落ちモデルが安く手に入る可能性もあるので狙い目です。
「今すぐ欲しい」と思う時期ほど、じつは避けた方がいいタイミングかもしれません。



セールよりも“静かな時期”を狙うのが賢い選び方。混雑と高価格をうまく避けてお得に買いましょう♪
適正サイズが電気代に与える影響
エアコンのサイズが適正でないと、意外と電気代に響いてしまうんです。
小さすぎるエアコンは常にフル稼働になるため、電気代が上がる原因になります。
逆に、大きすぎると短時間で冷暖房しようとするため、効率が悪くなります。
とくに冷房は、温度は下がっても湿度が下がらず、ジメジメ感が残ることも。
何度もオンオフを繰り返すことで、エアコン本体にも負担がかかってしまいます。
適正サイズであれば、無理なく一定の運転ができて、消費電力も抑えられます。
結果的に「効きがよくて節電にもなる」理想的な状態がつくれるんです。



エアコンも洋服みたいに“サイズ感”が大切。ピッタリだと快適だし、節約にもつながりますよ♪
まとめ|【後悔】エアコンの買ってはいけないサイズと選び方の落とし穴
最後にこの記事のポイントをまとめてご紹介します。
- エアコンは畳数だけで選ぶと実際の性能と合わないリスクがある
- 部屋の断熱性や日当たりによって必要なエアコン容量は変わる
- 適正サイズでないとエアコンの効きが悪くなり電気代が上がる
- 買ってはいけない時期は夏前や冬前など需要が高いタイミング
- 需要の落ち着く時期を狙えば型落ちモデルが安く手に入る
- 畳数表示は60年前の基準であり現代の住宅性能とは合わない
- 電気代節約のためには部屋に合ったサイズ選びが重要
- エアコンが小さすぎるとフル稼働で電気代と故障リスクが高まる
- 大きすぎるエアコンも効率が悪く結果的にコスパが悪い
- 最新モデルよりも自分の家に合う機種選びが満足度を上げる
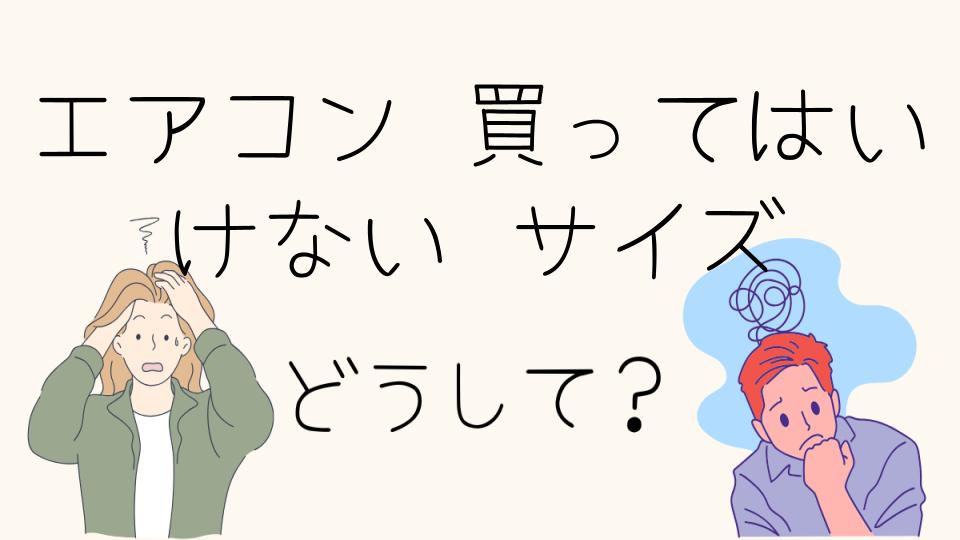
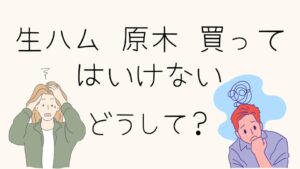
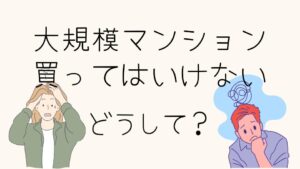
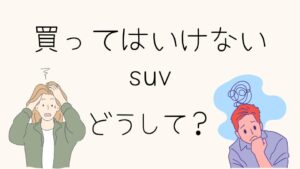
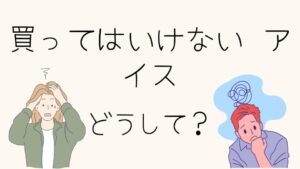
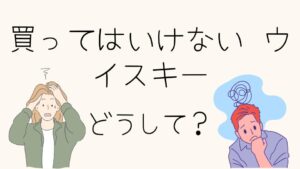
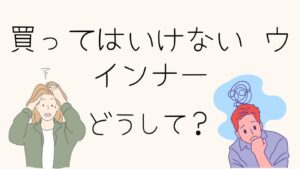
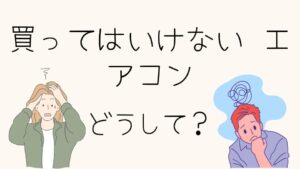
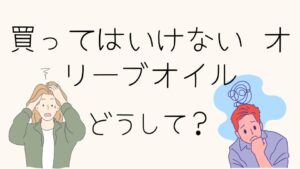
コメント